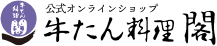仙台牛タンの歴史と閣

~はじまり~
店ごとに異なる独自の仕込みや味付け、調理法など「牛タン」という食材にバラエティを提供した、いわゆる「仙台牛タン」の歴史は古く、始まりは昭和23年に遡る。日本が戦後復興へと歩み始めた年に豊かな「仙台牛タン」の文化がスタート。名店「太助」の初代店主故・佐野啓四郎氏が洋食で使われていた牛タンの旨さの虜になり、試行錯誤の末、今なお定番となっている「牛タン焼き」が誕生。和食の職人でもあった佐野氏が包丁の入れ方、厚さ、塩の振り方などの仕込み、炭火の火力や焼き加減など、研究を重ねた結果、今も変わらない「仙台牛タン」のベースができあがったと言われている。
~きっかけ~
戦後間もない頃は、食糧難という状況もあり焼鳥屋さんでは鶏肉の他に、豚肉や牛肉など様々な材料を焼き料理として提供していたと言われている。当時、和食の職人として腕をふるっていた啓四郎氏は、調理方法が簡単な焼き料理はヒット商品が生まれても、次々と真似されてしまうことに悩み、親友に相談。「牛タンを出してみたら?」と提案され、まずは洋食屋でタンシチューを食べてみたところ、牛タンのもつ奥深い旨み衝撃を受け、啓四郎氏は「牛タン」という素材の虜になる。ここから、啓四郎氏の試行錯誤の日々が始まった。

~苦悩~
牛タンの研究をはじめて直面した問題。それは牛タンそのものが仙台市内ではほとんど売っていないということだった。啓四郎氏は牛タンを確保する為、県内の他、山形県へも足を延ばし、奔走する。ただ、一週間かけて県内や山形へ買い出しに行っても、牛タンは10本も集まらず、1本から牛タン焼きとして提供できる部分は25枚前後しかとれないということで、一人前3枚限定するなど、職人として1頭に1本しかない牛タンと牛テールをお客様に如何に美味しく、安定して提供できるか努力と試行錯誤を重ねた。
~仙台牛タン文化の誕生~
開発当初は牛タンの皮の剥き方も何もわからず、手には切り傷が絶えなかった。毎日、牛タン相手に悪戦苦闘しましたが、啓四郎氏は和食職人ならではのアイデアを思いつく。それが、牛タンを「切り身」にして塩味で寝かせてから焼く現在の手法。「牛タンの厚さ、包丁の入れ方、熟成する期間、塩の量や振り方、炭火の火力、そして焼き加減」など、あらゆる角度から研究を重ねた末、ついに仙台牛タン焼きが誕生する。

~閣の牛タン~

1988年、当時仙台で牛タンと言えば「太助、喜助」と言われた頃、この名店の大ファンだった「牛たん料理 閣」の初代店主中田敏弘が一般的だった定食としての牛タンではなく、 お酒と一緒に楽しめるコース料理風の牛タンを提供し始めることで、長い仙台牛タンの歴史に新しい風が吹く
閣の牛タンの最大の特徴ともいえる独特なカット技術は初代が試行錯誤を重ね、独学で開発したもの。また、「たたき」や「刺身」などの新しい調理法も生み出していきます。現在は100店舗を超えるといわれる「仙台牛タン」を提供するお店。その「仙台牛タン」の歴史と文化に豊かさと奥深さ、可能性を生み出したのが「牛たん料理 閣」だった。
~通販事業の思い~

「牛たん料理 閣」では、専門店ならではの味を日本全国の方にお届けしたい、いつもそんな思いはありましたが、職人が炭火で焼く牛タンと、ご家庭で焼く牛タンとでは味が変わってきてしまうことを懸念し、以前は地方発送も通信販売も行っておりませんでした。
しかし、ご来店頂いたお客様から「閣の牛タンを母に食べさせたいのに、足が悪くて・・・」「なかなか仙台まで来られないけれど、また食べたい」「遠方の家族に食べさせたい」といったお声を頂き、これは私たちの使命だと感じました。できる限り店舗の味を再現すべく試行錯誤を重ね、晴れて商品化が決定、通信販売、EC事業をスタートします。現在は大和町を拠点とする牛たん工房直売所にて、日々新たな商品開発に取り組んでおります。
私たちが提案する新たな牛タンの味わい方と可能性を、日本全国の皆さまにも楽しんで頂くことが何よりの喜びです。
 |  |